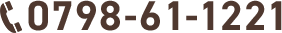Blog記事一覧 > 足について - 西宮市の整体なら阪急苦楽園口駅徒歩3分のKAIFUKU in 大~足、腰、自律神経の総合整体院~の記事一覧
5つのタイプの歩き方
今日は歩くときの「足の置き方」について、5つのタイプに分けて説明していきます。
1.足をそっと置く人
そっと足を置く人は、一見すると身体に受ける衝撃が小さいように見えます。
ただ、その理由が必ずしも良いとは限りません。
-
良いケース:股関節や体幹が安定していて、力みに頼らずに歩けている
-
注意したいケース:足裏を使いきれず、そっと置かないと不安定になる
2.トンと強めに置く人
地面を叩くようにトンと置くタイプです。
-
良いケース:リズム感が良く、体幹の軸が強い。特にスポーツでは推進力になる場合もある
-
注意したいケース:足裏のクッションを使えておらず、膝や股関節への衝撃が蓄積しやすい
「強く置く=悪い」ではなく、衝撃を吸収できる足の状態かどうかで意味が変わります。
3.つま先から置く人
つま先から置くのが癖の人は、ふくらはぎや足指に頼りやすい傾向があります。
-
良いケース:前への意識が強く、スピードに乗りやすい
-
注意したいケース:ふくらはぎが張りやすく、疲れやすい。外反母趾や足趾の癖が強くなることも
4.かかとから置く人
現代の靴の構造もあって、かかと接地の人はとても多いです。
-
良いケース:骨でしっかり支え、歩きのリズムが安定しやすい
-
注意したいケース:かかとに乗り過ぎて、体の後ろが重たくなり、前へ進む力を削いでしまう
「かかとから着くのが正しい」と聞いたことがある人も多いですが、体のタイプによっては逆に負担になることもあります。
5.真っすぐ置いているつもりで、少し外に流れている人
これは地面を蹴る際に、つま先が外に流れる人のことを言います。
自覚はなくても、足先が外に流れることで、膝や股関節のねじれが生まれやすくなります。
-
良いケース:外に流れているように見えて、実は全体のバランスが取れているパターン(高齢者に多い)
-
注意したいケース:足裏の内側が使えず、アーチが落ちやすい。結果として、股関節や腰の不調につながりやすい
本人は「まっすぐ置いているつもり」なので、気づきにくいです。動画で一緒に確認していく必要があります。
まとめ:表面的に良い・悪いを決めるのではなく、背景にある原因が大事
歩き方を見ていて思うのは、
足の置き方の癖にはほぼ必ず理由があり、それがその方の生活に合っているのかどうか、将来的にリスクがあるのかどうかを考える必要があるといことです。(アスリートは別)
結局は、身体の状態をひとり一人に合わせて整理しながら見ていくことが大切だと思っています。
-
アーチをしっかり作る方が良い人もいれば、アーチを落とした方が良い人もいる
-
静かな接地が合う人もいれば、しっかり接地のした方が安定する人もいる
-
親指で地面を蹴る方が良くなる人もいれば、それが負担になる人もいる
結局は、身体の状態をひとつひとつ整理しながら見ていくことが大切だと思っています。
西宮、夙川、苦楽園口、芦屋、宝塚で足の専門整体をお探しのかたは、足の専門治療院 KAIFUKUIN in 大 にお気軽にご相談ください。
足の機能が落ちてくると、思っている以上に全身へ影響が広がっていきます。
肩こりや腰痛でご相談に来られる方の中にも、実は足元の変化が原因になっているケースが少なくありません。
足の指が踏ん張れない、土踏まずが落ちている、体重が外側ばかりにかかっている、かかとからドスンと着地している。そうした小さな乱れが膝や股関節に負担をかけ、骨盤や腰の動きを乱し、やがて背中や肩の緊張につながるケースがあります。
足は体を支えるだけでなく、地面からの情報を神経を通じて脳へと伝える役割も持っています。そのセンサーが働かなくなると、膝や腰に負担が増えるだけでなく、バランスをとるために無意識に体幹を緊張させてしまい、自律神経が常に張り詰めたような状態になることもあります。すると疲れやすい、眠りが浅い、気持ちが落ち着かないといった不調まで広がってしまうのです。
また怖いのは、本人はなかなか気づけないという点です。年齢のせいだろう、体質だから仕方ない、と諦めてしまうことも多くあります。ただ、実際には足元の小さな乱れが引き金になっていることも多いのです。
当院では、まず歩行や足の動きを丁寧に確認し、必要に応じて足指の感覚を呼び戻すトレーニングや、アーチを支えるためのケア、体幹の安定性を高めるエクササイズなどを組み合わせていきます。
足元が変わると姿勢が変わり、全身のバランスも変わってきます。長引く肩こりや腰痛が「どこに行っても良くならない」と悩んでいる方ほど、まずは足から見直すことで改善の糸口が見えてくるかもしれません。
治るとは?健康を見失わないために
私たちのまわりには、身体に関する悩みがあふれています。
自律神経の乱れ、関節症、成長痛、腰痛、変形性膝関節症、肩や首のこり、頭の痛み…。
そして、それらを「治す」ために本当にたくさんの治療法が存在します。
数えきれないほどの治療法
マッサージ、筋膜リリース、ストレッチ、鍼治療、アナトミートレイン、AKA、PNF、アプライドキネシオロジー、エネルギー治療、気功、電気治療、カイロプラクティック、神経治療、呼吸、食事、瞑想、投薬、外科的治療、インソール、テーピング、カウンセリング、○○式…。
数え上げればきりがありません。
そしてこれからも新しい方法は生まれ続けるでしょう。
ただ、ここで少し立ち止まって考えてみたいのです。
手段と目的のすり替え
一つの痛みや不調、一つの治療法の枠の中にいるとき、私たちはまるで無敵のように感じることがあります。
それは、手段やルールに守られている安心感があるからです。
「この方法が正解だ」
「この技術で治せる」
そうやって先生と患者様の想いが一体になった瞬間に、
「患者様が良くなること」よりも「方法そのもの」が目的になってしまう危うさがあるのです。
専門性の大切さとその限界
もちろん、専門医や整体院を否定するわけではありません。
医療や施術が今後も前進するために、専門性を追求していくことはとても重要です。
当院も足や自律神経、姿勢を専門にしています。
しかし、人の身体も心も環境も常に変化していくものです。
「一つ良くなれば、また別の不調が出てくる」
そんなことは臨床の現場では日常茶飯事です。
健康を見失わないために
健康になるためのルールや方法は、とても大事です。
けれども、そのルールに縛られてしまうと、かえって気づけないこともあります。
大切なのは「治すための手段」ではなく「より良い状態で過ごせること」。
良いコンディションを作るための道は一つではありません。
当院では、その可能性を一緒に探し、学んでいくことを大切にしています。
西宮、夙川、芦屋、苦楽園口の整体院 KAIFUKU in 大 ~足、姿勢と自律神経の総合整体院~
膝痛、変形性関節症と腎機能(GFR)の関係
動画は変形性膝関節症の患者様の施術前後の歩行の変化です。
膝の痛みがひどく、ついに歩けなくなってきたとのお悩み
遠方よりご来院していただきましたが、1回の施術でかなり痛みが取れたということで喜んでいただけました。
ただ、変形性膝関節症や股関節症の中には、患部を治療するだけでは良い状態を持続することは難しいケースがあります。以下をご参照ください。
GFR(腎機能)という視点
変形性関節症や関節炎の治療というと、「膝の軟骨がすり減っている」「腰の関節に炎症がある」といった局所の問題に目が向きがちです。
しかし実際には、関節の治りやすさ・炎症の長引きやすさは 体全体の状態=全身因子 に大きく左右されることを考えなければいけません。
そこで考えなければいけない基準の一つにGFR(糸球体ろ過量)があります。
GFRは腎臓の働きを示す数値で、血液の中の老廃物を“フィルター”のようにこす力を表しており、60を切ると腎機能低下とされます。
腎機能が弱ると以下のような問題が現れます。
-
炎症を長引かせる
老廃物や炎症物質が体内にたまりやすくなり、関節の炎症が引きにくい。 -
骨の質が弱る
GFRが低下すると“腎性骨症”と呼ばれる骨代謝異常が進み、軟骨や骨の修復力が落ちる。 -
全身状態の低下
腎機能が悪いと、貧血や栄養不良が起こりやすく、関節の修復や筋肉の回復も遅れる。
このようにGFRが低値となると関節炎を長引かせるリスクが高まってしまいます。ですのでまずある程度の年齢になってくると、変形性関節症を治す場合は膝の問題を解決するべきか、全身状態を整えるべきか、優先順位を決める必要があると感じます。
早く対処しないと根本治療が難しくなる
糸球体(腎臓のフィルター)は、一度壊れると新しく作り直す能力はほとんどありません。
肝臓や皮膚のような強い再生力はなく、「不可逆的な臓器」とされています。
腎機能が低下している理由は人によって様々です。
ただ、軽度のダメージであれば、糸球体の細胞が修復して機能を取り戻すことがあるとも言われています。
当院では皆様のお身体を見させていただいた上で、ひとり一人に合った関節症のサポートをご提案させていただきます。
「年齢のせいだから仕方ない」と諦める前に、根本的に治していきたい。そんな想いをお持ちの方はぜひ当院はご相談ください。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方は当院まで。
歩き方に影響する要素はいろいろありますが、その中でも意外と見落とされやすいのが「目の使い方」です。
当院では問診時に、足や体の状態だけでなく、皆様の目の使い方にも注目して検査を行っています。
最近は、スマートフォンを下向きで見ている時間が長くなっており、目線が常に下を向いている方がとても多い印象です。
こういった目線のクセがあると、耳の後ろや後頭部の筋肉が緊張しやすくなり、次第に背骨のアライメントが乱れていきます。
その結果、膝が曲がったまま歩くクセにつながり、膝の痛みや腰の不調を引き起こすこともあるのです。
また、目の動きが固まってしまっている方は、視野が狭くなり、体も緊張しやすくなります。これは日常生活のストレスや姿勢のクセとも深く関係しています。
歩き方が気になるときは「目線」を見直してみましょう
「最近、歩く姿勢が悪くなってきた気がするな」
そう感じたときは、まず「自分がどこを見て、どんなふうに歩いているか?」を少し観察してみてください。
思わぬクセや偏りに気づくかもしれませんよ。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。
ジャンプには歩く・立つ・走るといった動作の基本が詰まっています。
ジャンプのコツはとてもシンプルです。
下半身で地面をしっかり押して、そのエネルギーをできるだけロスなく上半身に伝えること。
それだけです。
でも実際には、この“エネルギーの通り道”がどこかで止まったり、ブレたりしてしまうことで、思ったように跳べなかったり、かえって身体に負担がかかってしまうことがあります。
ポイントは大きく分けて3つあります。
1. 下半身で地面を「まっすぐ」押すこと
多くの方が、なんとなく力まかせに踏ん張ろうとしてしまいます。
でも大事なのは、足裏からつま先全体で地面を“押し返す”感覚。
その際に、足の裏や膝だけでなくお尻(臀部)の筋肉を使って押すことが重要です。
ここがうまく使えると、足裏→お尻→体幹へとエネルギーがスムーズにつながります。
2. 地面からの力を“まっすぐ”受け取るための軸
力は押すだけでは伝わりません。
それを受け取る側(上半身・体幹)に「軸」がないと、エネルギーが途中で抜けてしまうのです。
ジャンプをスローモーションで見るとよくわかりますが、うまく跳べている人は身体の中心に一本のラインが通っていて、ぶれません。
この軸は、腹圧・肋骨・首の位置など、全身の連動で自然と保たれます。
3. ジャンプは「動きの整理」にも使える
ジャンプ動作は、複雑なようでいてとても正直です。
無理な力の入り方やバランスの崩れは、そのまま「跳べなさ」として現れます。
だからこそ、歩行に不安がある方にとっても、ジャンプは身体の使い方を整理するシンプルなテストであり、リハビリのヒントにもなります。
もちろん関節障害がある場合は無理にテストすることは禁物ですが、、、
-
地面がちゃんと押せているか
-
エネルギーが上半身に伝わっているか
-
片足でのジャンプができるか
こうした動きの確認は、足の障害を見ていくうえでとてもヒントになると考えています。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。
幼少期の経験が、歩き方に残す影響
私たちが「今」どう歩いているかには、意外と子どもの頃の体の使い方が関係しています。
たとえば、こんな経験はありませんか?
-
ハイハイの期間が短かった
-
幼稚園や保育園で、あまり走り回らなかった
-
小さいころから靴を履く時間が長く、裸足で遊ぶことが少なかった
-
転びやすく、よく足元を気にしていた
これらの体験は、歩き方や姿勢の“土台”づくりに深く関わっています。
たとえばハイハイ。
実はこれ、肩や股関節、体幹を連動させて動く大切な動作です。
この時期に、身体の左右バランスや重心移動、手足のタイミングを自然と覚えていきます。
もしこの時期を飛ばしたり、早めに歩き出した場合、体幹や足の使い方にどこかアンバランスが残ることがあります。
また、外遊びの量や遊び方の幅も、足の感覚やバランス感覚に影響します。
「どう動くか」だけでなく、「なぜ動くのか」も大切です。
遊びや好奇心の中で、体を思いっきり使った経験があると、自然と姿勢がしっかりし、動きにも力みが少なくなっていきます。
逆に、「動くことが楽しくなかった」「外に出るのが億劫だった」といった背景があると、筋肉の使い方に偏りが出たり、体の一部に頼った動き方が身についてしまうことがあります。
こうした過去の体験は、今の歩き方や体の使い方に、少しずつ影を落としていることがあるのです。
もちろん、過去は変えられませんが、今からでも「自分の体の使い方を見直す」ことはできます。
もしご自身やお子さんの歩き方に不安を感じたら、まずは当院で歩行や足の発達の検査をしてみましょう。
当院では、現在の身体の状態とあわせて、そうした背景にも目を向けながら、無理のない形で体の使い方を整理整頓していくお手伝いをしています。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。
筋肉はただ鍛えるだけではうまく”歩けない” ”走れない” その理由とは
筋肉の強さは、歩き方や走り方にとって大切な要素のひとつです。ただ、筋トレをしているからといって「歩き方が良くなる」とは限りません。
実際に、ふとももやふくらはぎの筋肉はしっかりしているのに、変形性膝関節症や変形性股関節症、外反母趾、足底筋膜炎などによって痛みを抱えている方や、歩くとすぐ疲れてしまうとういようなお悩みの方が多くいらっしゃいます。
なぜでしょうか?
理由は「筋肉の強さ」だけではなく、「どう使われているか」がとても重要で、間違った動作を修正することができていないからです。
筋肉は、単独で動いているわけではなく、他の筋肉と連携しながら働いています。
どこかの筋肉が頑張りすぎていたり、逆にうまく使えていないところがあると、力の伝わり方が偏ってしまい、効率の悪い動きになります。
たとえば、
-
太もも前側ばかりを使っている人は、膝に負担がかかりやすい
-
お尻の筋肉がうまく使えていないと、歩幅が小さくなったり、バランスが取りづらくなる
-
ふくらはぎの力に頼りすぎると、足首が硬くなり、足裏に痛みが出ることもある
どこかの筋肉だけが過剰に働いていたり、逆にある筋肉がうまく使われていなかったりすると、動作に偏りが生じます。
すると、力の伝わり方にムラができて、本来かかるべきでない場所に負担が集中することになります。
この動作パターンを見直し、整理整頓していくことが、身体を本来の状態に近づけるための第一歩になります。
当院では、筋肉のバランスや力の入り方を一緒に確認しながら、「どう歩くとラクなのか」「どう使えば無理がかからないのか」を一緒に探っていきます。
「筋トレをしているのに、どうも歩きにくい」「昔より疲れやすくなった気がする」
そんな方こそ、今の歩き方や身体の使い方を見直してみる価値があると考えます。
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に
その歩き方、骨格のクセかも
骨格が動き方を左右する理由
歩き方や走り方は、その人の「骨格のクセ」が大きく影響しています。たとえば、骨盤の傾きや足の配列によって、重心の位置や足の運び方が自然と変わってくるのです。
実際に当院でも、初めての方の歩き方を見るだけで、おおよその身体の使い方や負担のかかっている場所が見えてくることが多くあります。
たとえば、こんな傾向があります。
-
骨盤が前に傾いている人は、反り腰気味になりやすく、腰まわりに負担が集中します。結果として、腰痛や張り感が出やすくなる。
-
反対に、骨盤が後ろに傾いている人は、上半身が後方に倒れやすくなり、バランスを取るために足に余計な荷重がかかります。すると、ふくらはぎや足裏が疲れやすくなったり、足の痛みが出やすくなる。
-
O脚の方は、足の外側ばかりを使いやすく、膝や股関節に負担がかかりやすい傾向がある。
-
X脚の方は、膝の内側にストレスが集中しやすく、偏平足になりやすい特徴があります。足全体の安定性が下がるため、歩行時にふらつきやすく、膝痛にもつながりやすくなる。
このように、骨格の特徴によって歩き方に「クセ」が生まれます。そしてこのクセが積み重なることで、疲れやすさや痛みといった形で体にサインが現れてくるのです。
では、こうしたクセは変えられるのでしょうか。
結論から言えば、完全に「治す」というよりも、体に合った「再教育」をしていくことが大切です。特に大人の場合、まずは今の体の状態になった理由を考えながら状況を整理整頓することが大事だと思っています。
自分の骨格に合った重心のかけ方、使うべき筋肉のバランス、無意識の姿勢のクセなどを見直していくことで、少しずつ歩き方・走り方は変わっていきます。
「なんとなく歩いている」状態から、自分の身体の使い方に気づくことが、第一歩だと思っています。
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に

お姉ちゃんは幅広のNew Balance 996
妹さんは少し狭めASICSアイダホ
見た目がそっくりなふたりでも、足の形や走り方にははっきりと違いがあります。
軽やかに走ったり、ペタペタ走ったり。
大人の目には「気になる」その違いも、子どもたちにとってはただ「楽しいから走ってる」だけ。今日も院内を走り回りこけて泣いてまた遊んで…笑
私たち大人ができることは、その“楽しい”を邪魔せず、自然な動きの中で成長につながるサポートをしてあげることだと思っています。
遊びの中に発育を促す工夫を。 小さな違和感が積み重ならないように、足に合った良い靴、遊びの環境を
「教える」のではなく、「整える」。 それが、小さな子どもたちにとっての最大のサポートになると思っています。
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に