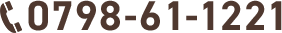子どもの頃、どうやって動いていましたか?
幼少期の経験が、歩き方に残す影響
私たちが「今」どう歩いているかには、意外と子どもの頃の体の使い方が関係しています。
たとえば、こんな経験はありませんか?
-
ハイハイの期間が短かった
-
幼稚園や保育園で、あまり走り回らなかった
-
小さいころから靴を履く時間が長く、裸足で遊ぶことが少なかった
-
転びやすく、よく足元を気にしていた
これらの体験は、歩き方や姿勢の“土台”づくりに深く関わっています。
たとえばハイハイ。
実はこれ、肩や股関節、体幹を連動させて動く大切な動作です。
この時期に、身体の左右バランスや重心移動、手足のタイミングを自然と覚えていきます。
もしこの時期を飛ばしたり、早めに歩き出した場合、体幹や足の使い方にどこかアンバランスが残ることがあります。
また、外遊びの量や遊び方の幅も、足の感覚やバランス感覚に影響します。
「どう動くか」だけでなく、「なぜ動くのか」も大切です。
遊びや好奇心の中で、体を思いっきり使った経験があると、自然と姿勢がしっかりし、動きにも力みが少なくなっていきます。
逆に、「動くことが楽しくなかった」「外に出るのが億劫だった」といった背景があると、筋肉の使い方に偏りが出たり、体の一部に頼った動き方が身についてしまうことがあります。
こうした過去の体験は、今の歩き方や体の使い方に、少しずつ影を落としていることがあるのです。
もちろん、過去は変えられませんが、今からでも「自分の体の使い方を見直す」ことはできます。
もしご自身やお子さんの歩き方に不安を感じたら、まずは当院で歩行や足の発達の検査をしてみましょう。
当院では、現在の身体の状態とあわせて、そうした背景にも目を向けながら、無理のない形で体の使い方を整理整頓していくお手伝いをしています。
~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~ 専門的な治療をつなげ、効果を最大限に
西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方はご相談ください。